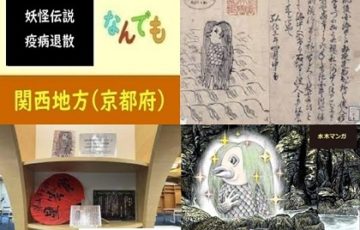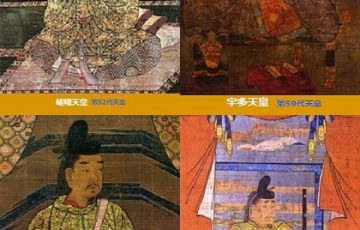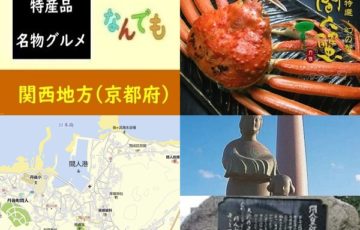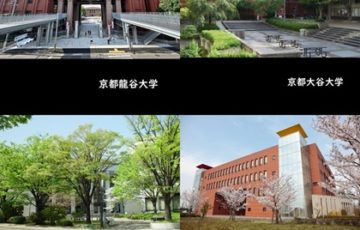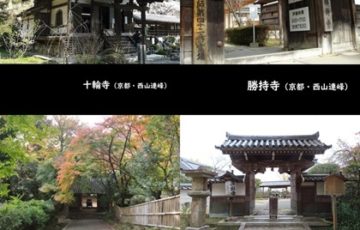【食育クイズ:Vol.913】
本日も、「関西地方(三重県、滋賀県、
和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府、
大阪府)」の「食文化」をテーマとし
た地域社会の在り方や、昔から先人た
ちが培ってきた、文化や伝統、歴史等
の素晴らしさを、クイズを楽しみなが
ら知見を高め、共有して参りましょ
う!
さて、本日は、「京都府」の「酒器」文化
について、おさらいクイズ(Vol.124)
にチャレンジ致しましょう!
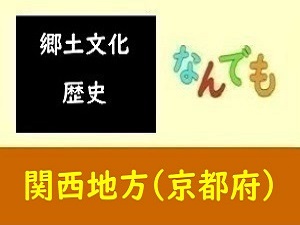
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「酒器」とは、酒を入れて注いだり、酒を
飲むための容器の総称の事を言います。
「古代」の酒器は、「木の葉」、「木の実」、
「牛の角」、「竹筒」等々…、自然のものを
使用していた事から始まったと言われてい
ますが、日本では、主として「カシワの葉」
が「食器」や「杯」として使用されていた
ようです。
その後、「土器」が作られるようになると、
音読みで言うと「かわらけ(土器)」と呼
ばれるものに変わっていったと言われてい
ます。

以来、「かわらけ(土器)」は、「古墳時代」
以降の「遺跡」から出土する「土師器(は
じき)系統」の「皿形」や「碗形」の土器
に対する用語としても使われていて、現在
でも、「神事」の際に「かわらけ」と言う
言葉が用いられる事があるのは、昔ながら
の名残であると言う事になります。
「奈良時代」になると「金、銀、金銅(こ
んどう)、めのう」等の素材を使った「酒
器」が見られるようになり、「平安時代」
になると、「木製」の「朱漆塗り」の「杯」
が登場し、それが次第に一般化していき、
現在では「杯」と言えば、「朱塗りの木杯」
を指すようになっていると言う経緯があり
ます。

さて、本日は、「京都」の「神事」や「行
事」等で使用されてい「酒器」について、
おさらいクイズにチャレンジしましょう!
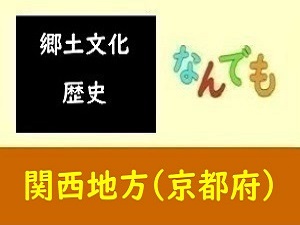
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
一般的に素焼きの「土器(かわらけ)」で
作った「酒杯」は、古代から「室町時代」
頃までの間、広く使われていたと言われて
います。
「平安時代」以降になると、「貴族」や
「武家」の社会では、基本的な「酒杯」の
「献立や作法」として、「式三献」と呼ば
れる儀礼が定着するようになり、これは、
一つの「肴の膳」と、三口で飲む「酒」と
の組み合わせを一献として、これを三度繰
り返す儀礼の事を言うそうです。
ちなみに、現在でも「神前の結婚式」では、
「杯」をやりとりして契りを結ぶ「三三九
度」の儀式をしますが、これはこの「中世」
の儀礼だった「式三献」を習ったものであ
り、杯に「三回」酒を注ぎ、その酒を「三
口」で飲み、さらに杯を変えて「三度」繰
り返すと言うものです。
この婚礼の「三三九度」の儀式や、新年の
「屠蘇」等には、現在でも「蒔絵」で「吉
祥文様」を施した朱塗りの重ね杯が用いら
れているのは、中世以降から継承されてき
た「儀礼」が元になっている訳になります。


さて、それでは、「京都」で使われていた
「酒器」について、おさらいクイズにチャ
レンジしましょう!
問題:日本酒を注ぐための「酒器」は色々
ありますが、その中でも、「中世」の「京
都」で、「神事」や「宮中儀式」等で使用
されていた、日本酒を注ぐための「酒器」
とはどれでしょうか?
次のうちから選んで下さい。
1.銚子

2.徳利

3.片口

4.ちろり

↓↓↓↓↓答えはここから↓↓↓↓↓
【解説】
「銚子(ちょうし)」とは、長い柄のつい
た「酒器」の事を言い、中に「お酒」を入
れて「盃」に注ぐ際に使われるもので、
「神事」を始め、あらたまった「酒宴」や、
「三三九度」等の儀式に用いる、長い柄
(え)のついた金属や木製の器の事を言い
ます。



かつて「宮廷」の「祝宴」で使われていた
「銚子」は、一箇所に注ぎ口のある「片口」
と呼ばれるものだったそうで、その一方、
大勢で酒盛りをする時等では、略式として
「両口」のもの使用し、効率良く左右の口
から盃に注げるものを使用していたと言わ
れています。
「銚子」は、主に「金属製」のものが多か
ったそうですが、「木製」のものや「磁器
製」のものも珍しくは無く使われていたと
言われているそうです。


ちなみに、現在では、宴席等で「お銚子一
本!」とオーダーする様子が見受けられま
すが、実際にこのように頼んでも、古来か
らある本来の「お銚子」が出てくる訳では
無く、いわゆる「徳利」で出てくる事が多
いので、「銚子」と「徳利」とは、本来的
に別の酒器であるのに、混同されて呼ばれ
ていると言う訳になります。
また、急須のような形をしたものについて
は、本来「提子(ひさげ)」と呼ばれてい
たものが、「江戸時代」頃から「銚子」と
も呼ばれるようになっていったそうで、現
在では「お正月」の「お屠蘇」を飲む時等
に多く使われています。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「徳利」とは、首が細くて胴体が膨らんだ
独特の形状が特徴の「酒器」です。注いだ
時に「とくとく」という音がすることから
名が付いたという説もあるそうです。
かつては小さなものから一升瓶までのサイ
ズが揃い、「醤油」や「酢」等の貯蔵や運
搬にも幅広く使われていましたが、現在で
は、1~2合(180~360ml)程度の容量
のものが主流となっています。




∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「片口(かたくち)」とは、口縁の片側に
注ぎ口がある「酒器」の事を言います。そ
の歴史は古く、「縄文土器」や「弥生土器」
にも見受けられています。

日本酒を「盃」に注ぐ容器として使われて
きたと言う経緯がありますが、口径が広く
蓋がないので、熱が冷めやすく燗酒には不
向きですが、ひや酒や冷酒には使いやすい
酒器と言う事になります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「ちろり(銚釐)」とは、日本酒を温める
容器の事を言います。
真鍮や銅、錫などの素材を使い、熱伝導性
が良く、「ちろり」とすぐ温まることから
命名されたと言われているそうです。

「京都」では「たんぽ」と呼ばれることも
あるそうで、「徳利」のように鍋に入れて
温めたり、氷に埋めて「冷酒」にして酒を
楽しめる「酒器」として重宝されている
「酒器」だと言われています。
↓↓↓↓↓↓↓答え↓↓↓↓↓↓↓
1.銚子
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪市立大学の研究グループが、大豆
などに含まれるイソフラボンが肺気腫
や慢性気管支炎などの「COPD(慢性
閉塞性肺疾患)」の予防効果を有するこ
とを明らかにしました。
食Pro.お薦めの「大豆ミート」は、
少量摂取でも人にとって必須な「タン
パク質」「食物繊維」「核酸」などの栄
養素が摂取できるように、大豆の油脂
分を除いてから作っています。
必要な栄養素が原料大豆の約1.2倍
以上となり、濃縮された分だけ、多く
含まれています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★大豆プロテイン100g中に植物性
たんぱく質が50g!(半分がたんぱ
く質です)
★低脂質(2.7g)です!
★高食物繊維(20g、腸内発酵を促進
し、腸内健康の源となります。)
これを毎日食すると腸内発酵が促進さ
れ、お通じが良くなり、腐敗から発酵
にチェンジするので、おならが臭くな
くなります。
デドックス効果で身体もスッキリ!!
每日の食で「医者いらず!薬いらず!」
低脂質!ダイエットに最適な高たんぱ
くプロテイン!
国産の遺伝子組み換えでない大豆だけ
で作った「みそちゃんおじさんオリジ
ナル」の「スーパープレミアム大豆プ
ロテイン」です!
毎日の食に取り入れ、病気になりにく
い若々しい体を維持しましょう!

↓↓↓↓↓ここから入手!↓↓↓↓↓
青森産大和しじみのお味噌汁!限定徳
用セットはここから入手!↓↓↓↓↓

https://6jika.thebase.in/items/25021970
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
国産の食応援「和乃家(わのか)」は、
日本の食の安全保障として日本人の命
と健康を守る活動をしています。大豆
ミートをはじめ、食に関するいろいろ
な情報を発信していますので、よろし
かったら一度遊びにきてくださると嬉
しいです。「いいね」もしてくださる
と、情報更新のお知らせが届くように
なりますのでなお嬉しいです。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓